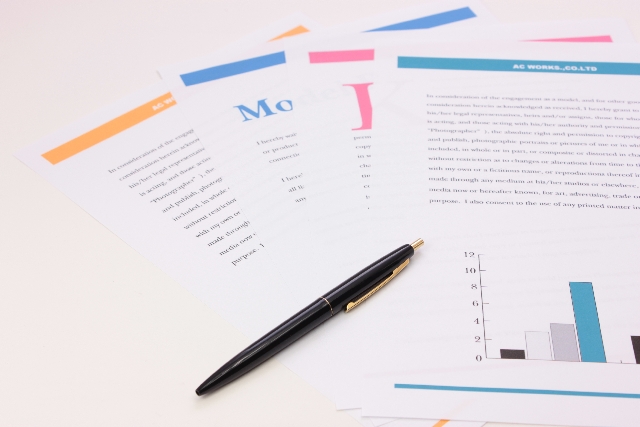


国民年金の手続きについて教えてください!
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
①可能です。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
退職後の国民健康保険の手続きについて
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。
また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
国民健康保険なんて入らなくていいです。
ものすごい保険料を取られます。
最大で65万円!!!!
1ヶ月くらいで死ぬような病気は無いです。
最悪全額負担しても65万円にもなりません。
ものすごい保険料を取られます。
最大で65万円!!!!
1ヶ月くらいで死ぬような病気は無いです。
最悪全額負担しても65万円にもなりません。
私は34歳の主婦です。小学5年生の息子と主人と3人で暮らしてます。
主人が失業して7ヶ月過ぎました。未だ再就職決まらず、失業保険も先月で打ち切りになりました。
生活を支えるため、私は水商売をしてるのですが、体が限界にきてます。主人に言っても、心配してるような言葉は言うけど、アルバイトすらしようとはしないんです。
姉さん女房で、何でも私が決め、引っ張ってきたので甘えてるのかな?と思うんですが・・もう、体力的にも精神的にも限界です。失業を経験されたご主人・奥様アドバイスお願いします。どうしたら、バイトしてくれるのでょうか?
主人が失業して7ヶ月過ぎました。未だ再就職決まらず、失業保険も先月で打ち切りになりました。
生活を支えるため、私は水商売をしてるのですが、体が限界にきてます。主人に言っても、心配してるような言葉は言うけど、アルバイトすらしようとはしないんです。
姉さん女房で、何でも私が決め、引っ張ってきたので甘えてるのかな?と思うんですが・・もう、体力的にも精神的にも限界です。失業を経験されたご主人・奥様アドバイスお願いします。どうしたら、バイトしてくれるのでょうか?
このまま甘え続けられても困りますからいっそのことあなたが仕事を辞めては。
そうすればだんなさんももっと真剣に職探しするんじゃない?
そうすればだんなさんももっと真剣に職探しするんじゃない?
今まで失業保険を受給していたので、国民健康保険証だったのですが、保険の受給が終了したので主人の扶養に入ります。
この場合、主人の会社から保険証をもらうことになると思うのですが、今手元にある国民健康保
険証はどうしたらよいのでしょうか?
お分かりになるかた、ご返答を宜しくお願いいたします。
この場合、主人の会社から保険証をもらうことになると思うのですが、今手元にある国民健康保
険証はどうしたらよいのでしょうか?
お分かりになるかた、ご返答を宜しくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者の健康保険証が届いたら、国保の保険証と一緒に、市区町村の国保担当課に出向いてください。
そこで被扶養者の保険証に記載されている、扶養認定日付で、国保をやめる手続きをします。
なお保険料の支払い等の確認を、必ずその場でしてください。
そこで被扶養者の保険証に記載されている、扶養認定日付で、国保をやめる手続きをします。
なお保険料の支払い等の確認を、必ずその場でしてください。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。
早速ですが、下記をご参照下さい。
≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。
退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日
国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月
無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)
妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬
以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。
昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。
<任意継続保険料について質問>
①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?
<生命保険と国民年金について質問>
④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。
知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
関連する情報